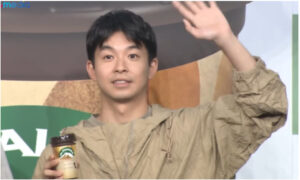元欅坂46のセンターとして圧倒的な存在感を放ち、卒業後も女優、歌手、ダンサー、モデルとして独自の表現を追求する平手友梨奈さん。
彼女の「歌い方」についてはファンの間で様々な意見がありますが、特に2025年7月2日放送の『2025 FNS歌謡祭 夏』が大きな話題となりました。
番組で披露した光GENJI「ガラスの十代」のカバーに対し、「歌ってない」「口パク?」といった疑惑の声が上がったのです。
なぜ彼女のパフォーマンスは「口パク」や「下手」と見られてしまうことがあるのでしょうか。
「歌ってない」「ガラスの十代 口バク」「ガラスの十代 下手」「歌唱力」「ガラスの十代 動画」「歌い方」といったキーワードを基に、ネット上の両論を比較しながら、その背景を探っていきます。
FNS歌謡祭「ガラスの十代」パフォーマンスの概要

平手友梨奈さんは、番組で光GENJIの名曲「ガラスの十代」をカバー。デニム衣装にオリジナルの振り付けをアレンジし、低音ボイスでクールに披露しました。
このパフォーマンスは事前収録でしたが、放送直後から「ガラスの十代 動画」の検索が急増。YouTubeにも複数のパフォーマンス動画がアップされ、大きな注目を集めました。
動画では、彼女の表現力に対して「中森明菜の再来」と称賛する声が上がる一方、コメント欄では「口の動きが音と合わない」「歌ってないように見える」といった指摘も出始めました。
賛否両論!「口パク」か「生歌」か

平手さんの歌に関する議論は欅坂46時代からありましたが、今回のFNSでのパフォーマンスで特に注目を集めました。ネット上の「口パクだ(歌ってない)」という意見と、「歌っている」という意見、それぞれを見ていきましょう。
【口パクだ(歌ってない)という意見】
ネット上では「収録でカバー曲なのに口パク?」「激しい振り付けでもないのに口パクっぽい」といった声が上がっています。
また、YouTubeのコメントやYahoo!知恵袋などでは、「口があまり動いていないように見える」という具体的な指摘もありました。
欅坂46時代のイメージも影響しているようで、「ゴリゴリに口パクっぽかった」「がっかりした」と、ソロになってもスタイルが変わっていないのでは、と残念がる声も聞かれます。

【歌っている(擁護する)という意見】
一方で、芸能ジャーナリストからは「口パク疑惑の指摘はどうか」と擁護する声も出ています。あるジャーナリストは、欅坂時代から歌唱力は評価されており、音楽フェス「JAPAN JAM」では安定した生歌を披露した、と分析しています。
X(旧Twitter)では「力強さとかっこよさの中に繊細さがある」「ちゃんと原曲を大事にしたアレンジでかっこいい」といった賛辞も多く寄せられています。
ファンからは「透明感のある低音ボイス」「表現力がずば抜けてる」という声が根強く、テレビ番組では音響の都合などで口パクや「被せ(音源を流しながら歌うこと)」が主流である、と指摘する意見もあります。
なぜ「口パク疑惑」が生まれるのか?

ソロアーティストとして活動する彼女にとって、「歌ってない」という疑惑は大きなデメリットのはず。では、なぜ繰り返しこうした声が上がるのでしょうか。
そこにはいくつかの理由が考えられそうです。
1. 独自の「歌い方」と見た目のギャップ
平手さんのパフォーマンスは「表現力重視」で、低音ボイスや感情を爆発させるようなスタイルが特徴です。これが、人によっては「音程が不安定」「声量が足りない」と見えてしまい、「ガラスの十代 下手」といった評価につながっているのかもしれません。
また、息継ぎや口の動きが音源と微妙にズレているように見える瞬間が、「口パク」と判断される原因になっているようです。
2. テレビ番組の特性と事前収録
音楽番組、特に生放送では、放送事故を避けるためや音響の都合上、事前収録や音源を使用することが一般的です。今回も事前収録だったことが、「本当に歌っているのか?」という疑惑を大きくした面もありそうです。
3. 過去のイメージの影響
欅坂46時代、激しいダンスパフォーマンスが多いため、口パク(または被せ)で歌うことが多かったのも事実です。その頃のイメージが今も影響し、「どうせ口パクだろう」という先入観を持って見られてしまうのかもしれません。
まとめ:疑惑の向こう側にある「表現者・平手友梨奈」
平手友梨奈さんの「歌い方」は、賛否が分かれること自体が、彼女の持つ独特な魅力の裏返しとも言えます。
口パク疑惑は、彼女の過去のイメージや独自のスタイルから生まれていますが、両方の意見を見比べ、音楽フェスなどでの生歌の実績を考えると、FNSでのパフォーマンスも彼女なりの表現方法だったと考えるのが自然かもしれません。
実際に「ガラスの十代」の動画を見て、ご自身で判断してみるのも面白いでしょう。
2025年8月には初のワンマンライブも控えるなど、彼女はこうした議論を超えた場所で、表現者として進化を続けています。
 おくやま
おくやま管理人の「有為之おくやま」です。
記事をまとめながら、あの低音ボイスの響きに改めて聴き入ってしまいました。 「中森明菜の再来」という評価、個人的にはすごくしっくり来ています。 口パクかどうかなんて些末なこと。あの世界観に一瞬で引き込まれた時点で、表現者としての彼女の勝ちですよね。
賛否両論すらもエネルギーに変えて、これからも唯一無二の道を突っ走ってください!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
☆おすすめ記事☆