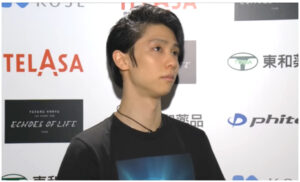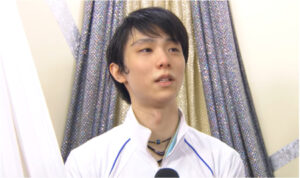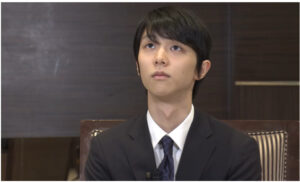アイナ・ジ・エンドは、元BiSHのメンバーとして知られ、独特の歌声とパフォーマンスが魅力のアーティストです。女優としても活躍する彼女ですが、2024年にリリースした楽曲「宝者」のミュージックビデオ(MV)が、大きな「炎上」騒動に発展しました。
「宝者」はTBSドラマ「さよならマエストロ~父と私のアパッシオナート~」の主題歌としても話題になりましたが、問題となったのはMVで取り入れられた「手話」の表現です。
この手話を交えたダンスが、ろう者(耳の聞こえない方々)のコミュニティから「言語をダンスの道具として消費している」と厳しい批判を受けたのです。手話はろう者の大切な「言語」であり、文化です。善意の試みだったはずが、なぜ配慮不足と受け止められてしまったのでしょうか。
この記事では、「炎上」「手話」「宝者」「ダンス」のキーワードをもとに、何が問題だったのか、賛否両論の意見を整理します。
炎上の発端:「ダンスでした」という発言

「宝者」のMVは2024年2月5日に公開されました。寒空の下で手話を交えて踊る姿が印象的な映像です。
火種となったのは、アイナさん本人のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」(2月27日放送)での発言でした。彼女は「手話は振り付けと同じ感覚で、ほぼほぼダンスでした」「『少し』っていう手話が好きで、奥ゆかしくて可愛らしくて」と語りました。
この発言がYahoo!ニュースなどで広まると、3月上旬からX(旧Twitter)で、ろう者や手話関係者から批判の声が一気に噴出。ろう者である写真家の斉藤義道氏の投稿が5,000リツイートを超えるなど、大きな注目を集めました。
問題の核心は、「宝者」のMVで「手話」を「ダンス」の一部として扱った点です。ろう者の方々から見ると、その動きは意味の通じない「手話風ダンス」であり、大切な言語が軽視されている、と受け止められたのです。
なぜ批判されたのか? ろう者の視点

批判の多くは、ろう者コミュニティから上がりました。彼らにとって手話は単なるジェスチャーではなく、独自の文法を持つ大切な「言語」(日本手話=JSL)です。
主な論点は以下の通りです。
- 言語としての意味が通じない
MVの動きは「意味をなしていない」部分が多く、ろう者にはメッセージとして伝わりません。「手話風」の雰囲気だけが、健常者向けの「自己満足」なエンタメとして消費されている、という怒りです。 - 「文化的盗用」という視点
NPO法人「インフォメーション・ギャップ・バスター」の伊藤芳浩氏は、「手話をおもちゃにしないで」と強く非難しました。これは、マジョリティ(健常者)がマイノリティ(ろう者)の文化を、その背景や当事者の想いを無視して利用する「文化的盗用(アプロプリエーション)」だという指摘です。 - 手話歌トレンドへの違和感
近年、TikTokや学校教育で「手話歌」が流行していますが、その多くはろう者の意見を反映せず、健常者の自己表現ツールになっている側面があります。ドラマ『silent』(2022年)のような丁寧な手話の扱いとは対照的だ、という意見もありました。
Xでは、ろう者から「音楽の概念がない私たちにとって、手話歌は不快」という切実な本音も投稿され、根深い問題であることがうかがえます。
擁護の意見:「表現の自由」と「普及のきっかけ」

一方で、アイナさんを擁護する意見も少なくありませんでした。
- 悪意はなく「善意の試み」
多くの人が「アイナ本人に悪意はなかったはず」と指摘。手話を学ぼうとした温かい試みであり、これを機に手話が広まる良いチャンスだ、と捉える声です。Xでは「炎上してるけど、今後も手話にチャレンジしてほしい」といった応援も見られました。 - 表現の自由の範囲内
あるnoteの執筆者は、「言語の一つとしてエンタメ化することを問題視しすぎるべきではない」と主張。過去に酒井法子さんの「碧いうさぎ」(1995年)がドラマと共に手話を広めた例もあり、過度な批判は新しい表現を萎縮させてしまう、という意見です。 - 「手話風ダンス」として楽しむ自由
ネット上では「単に手話風のダンスとして楽しめばいいのでは?」「炎上が過熱しすぎている」といった、批判を「過剰反応」と見る向きもありました。
まとめ:炎上から見えた「視点の違い」と今後の課題
この「宝者」をめぐる炎上騒動は、2024年3月頃には収束に向かいました。アイナさん本人や事務所からの直接的な謝罪や公式声明は、調査した限り見当たりませんでした。この「沈黙」が、さらなる誤解を招いた面もあるかもしれません。
今回の騒動の根本にあるのは、手話を「言語」と捉えるろう者と、「表現(ダンス)」の一つとして捉えた健常者との「視点の違い」です。
批判側の「文化の盗用」という指摘も、擁護側の「表現の自由」や「普及のきっかけ」という意見も、それぞれに理があります。
大切なのは、TikTokなどで手軽に文化が消費されがちな今、表現に取り入れる際には「監修」や「当事者の参加」がいかに重要か、ということです。
アイナさんのケースは、悪意のない行動が知らず知らずのうちに誰かを傷つけてしまう典型例として、社会に大きな議論を投げかけました。この騒動が、手話への理解を深める「きっかけ」になることが望まれます。
 おくやま
おくやま管理人の「有為之おくやま」です。
記事を書きながら、表現の世界の奥深さと難しさを改めて感じました。 批判はありましたが、アイナさんが手話に「美しさ」や「可愛らしさ」を感じた感性そのものは、決して否定されるべきではないと思います。
失敗から学び、より深く理解することで、表現はもっと豊かになるはず。 いつかまた、誰もが納得する形で、彼女なりの手話パフォーマンスを見せてくれることを期待して応援したいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
☆おすすめ記事☆